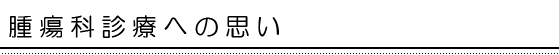
『小さなしこりだから大丈夫でしょ?』
『様子をみてたらしこりが消えないかな?』
『きっと虫に刺されただけだよ…ね?』
ワンちゃん、ネコちゃんのしこりを見つけても、
このように受け止めていることが多いのではないでしょうか。
また、『腫瘍』≒『もう助からない』というイメージも強いと思います。
それは、腫瘍の診断・治療が後手に回ってしまった場合のことです。
腫瘍だったら怖い。
だからしこりの正体を突き止めるのを後回しにしよう…
という気持ちは誰しも持っているものです。
しかし、早期に見つけ、適切な診断・治療ができれば、
治せる腫瘍や、痛みや苦しみを抑えつつ長く付き合える腫瘍もたくさんあります。
ワンちゃん、ネコちゃんの寿命が伸びるとともに
ペットの2~3頭に1頭は腫瘍で亡くなる時代になってきました。
これは人間と変わりありません。
もちろん『早期発見、早期治療』がポイントであることも人間と同じです。
しかし、体調の異変を話せないペット達の腫瘍を
『早期発見』するのは容易ではありません。
腫瘍の80%は体の表面にできます。
ちょっとしたしこりでも見つけたらご相談ください。
残りの20%は体の内部にできます。
なんとなく体調が悪い、治療中の病気がイマイチ良くならない…など、
体内の腫瘍のサインかもしれません。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
治せる腫瘍は、適切に治療し、長期にわたり再発のチェックを!
治せない腫瘍は、苦しむことなく穏やかに過ごせるように工夫を!
命に関わる病気だからこそ、動物-ご家族-獣医師の連携が非常に重要です。
1頭でも多くの子の腫瘍を治し、治せない子も穏やかに最期を迎えられるように!
それが、私達の願いです。
獣医師・宮澤 裕
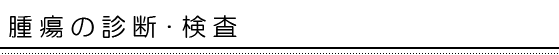
腫瘍にはたくさんの種類があります。
放置しても良いものから、急いで治療に入るべき危険なもの、
発見した時点で余命の短いものまでいろいろです。
『しこり』の見た目で、どの腫瘍か決め付けることは危険です。
ワンちゃん、ネコちゃんに負担のかからない検査から始め、
『腫瘍の正体』を突き止めること、
『全身のどこまで』腫瘍の影響を受けているのか把握すること、
この2点が腫瘍との闘いの始まりです。
見た目で『良性ですね、放置しましょう』と言えることはありません。
![]()
ワクチンで使う細い針で、しこり内の細胞を少し採取します。
その細胞を顕微鏡で確認し、どの腫瘍か評価します。
特徴的な細胞であれば診断に至りますが、ごく少量の細胞なので、
『おそらく良性』や『たぶん悪性』としかわからない場合もあります。
![]()

やや太目の針で、
しこりの内部をくり抜きます。
採取される細胞の量が増えるため、
診断精度が高まります。
しこりの内部には神経がないため、
痛みはありません。
![]()

麻酔下での小規模な手術でしこりの一部を切除し、
病理検査によってしこりの正体を突き止めます。
半端にメスを入れると悪化する腫瘍もあること、
麻酔をかける必要があることから、
頻繁に行う検査方法ではありません。
![]()
 採取した細胞や、切除した組織を
採取した細胞や、切除した組織を
顕微鏡の専門家に評価してもらいます。
これにより腫瘍の正体がわかれば、
最適な選択肢を選ぶことができます。
また、外科手術で摘出した組織も病理検査を行い、
補助治療の必要性などを評価します。
摘出した組織の病理検査をしないのは危険です。
![]()
上記の検査は、『腫瘍の正体を知るための検査』でした。
レントゲンやエコーは、『腫瘍があるかどうか』の検査です。
体内の腫瘍を探したり、他の臓器にできた腫瘍が
肺転移していないか探したりが目的となります。
手術後の経過チェックとして胸部の撮影をすることもあります。
![]()
レントゲンと同様に、『腫瘍を探す』ための検査ですが、
エコーは内臓の内部の腫瘍を探します。
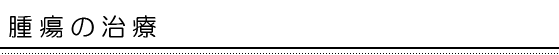
外科手術、化学療法、放射線治療が『がん治療の3本柱』です。
腫瘍の種類によって、効果のある治療法が異なります。
腫瘍の種類を正確に診断してから、
最も効果的な治療法を選ぶことが重要です。
また、治療法によってその副作用も異なります。
『腫瘍』≒『副作用との闘い』というイメージをお持ちの方も
少なくないと思います。
しかし、それぞれの治療法に特有の副作用を把握し、
その対策をしていれば、それほど怖い思いをせずに
拍子抜けされることも多く経験します。
![]()
 麻酔下での外科手術で腫瘍の摘出を行います。
麻酔下での外科手術で腫瘍の摘出を行います。
腫瘍を直接切り取るので、最も即効性があります。
そして、すべての腫瘍細胞を摘出できれば、
全くの健康体に戻れます。
しかし、他の内臓に転移している場合や、血液の腫瘍など
手術では取りきれないものも多くあります。
また、悪性の腫瘍ほど、しこりそのものよりも
大きく切除する必要があります。
![]()

腫瘍細胞の数を減らすことが目的であり、
完全にゼロにすることはできません。
血液の腫瘍などでは、かなりの効果が期待できる
腫瘍もたくさんあります。
また、手術後の補助として使用することもあります。
効果を高め、副作用を抑えるために、
腫瘍の種類、健康状態などに合わせて選択・調節します。
![]()

腫瘍細胞に放射線を照射することで治療します。
照射部位の皮膚炎を起こすことがありますが、
脳内や、鼻の中など、手術ができない部位の
腫瘍にも照射できます。
放射線治療を行う場合は、大学病院で
放射線治療専門医が治療を担当いたします。
![]()

体内の免疫細胞を利用して、腫瘍細胞だけを攻撃するように
教育し、腫瘍を攻撃するのが免疫療法です。
免疫療法にもいくつかの方法がありますが、
基本的には本人への副作用がありません。
しかし、効果が期待できる腫瘍の種類はまだほんの一部です。
腫瘍治療の3本柱でもダメな場合の選択肢として
今後に期待される分野です。
![]()

腫瘍細胞は42.5℃以上の温度で死滅するという
性質を利用した治療法です。
レーザーを用いて腫瘍組織を温めますが、
正常な細胞はなんとか耐えられる温度なので、
軽いやけど程度の副作用しかありません。
メインの治療法として活躍するものではありませんが、
腫瘍治療の補助としての有効性が報告されています。
腫瘍の診断・治療に関しての大まかなご説明でした。
繰り返しになりますが、『早期発見・早期治療』が非常に重要です。
特に『正確な診断』をすること、それに合った
『適切な治療の選択肢』を選ぶことが重要です。
長生きさんが増えるにつれ、腫瘍になる子が増えています。
しかし、腫瘍を克服できた子も増えてきています。
気になることは先延ばしにせず、お気軽にご相談ください。



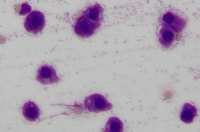
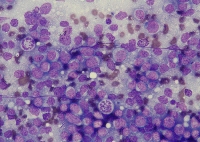

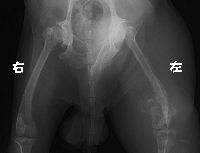
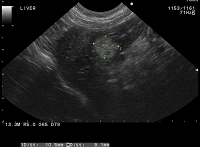
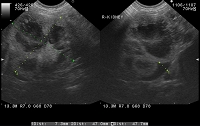
 アクセス
アクセス





