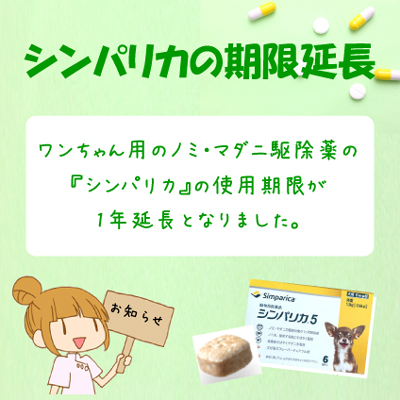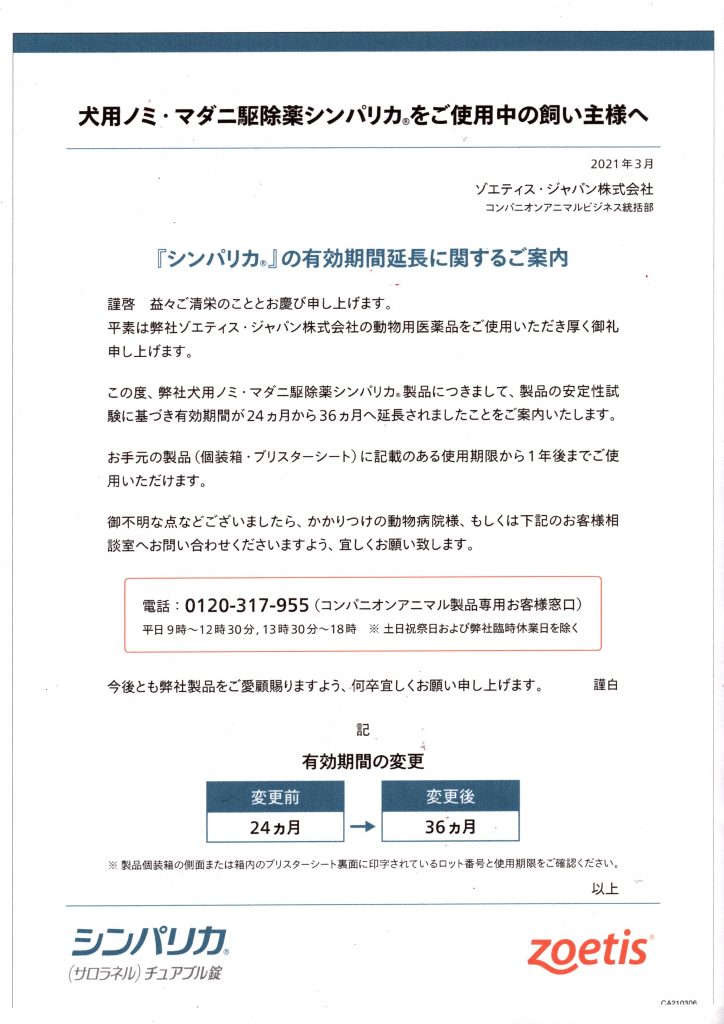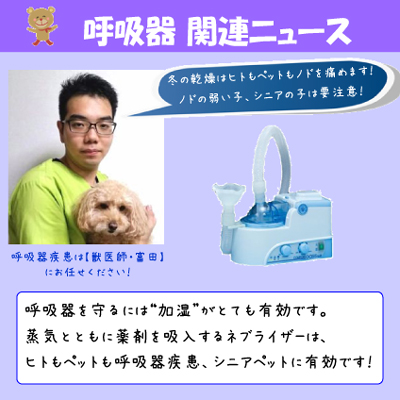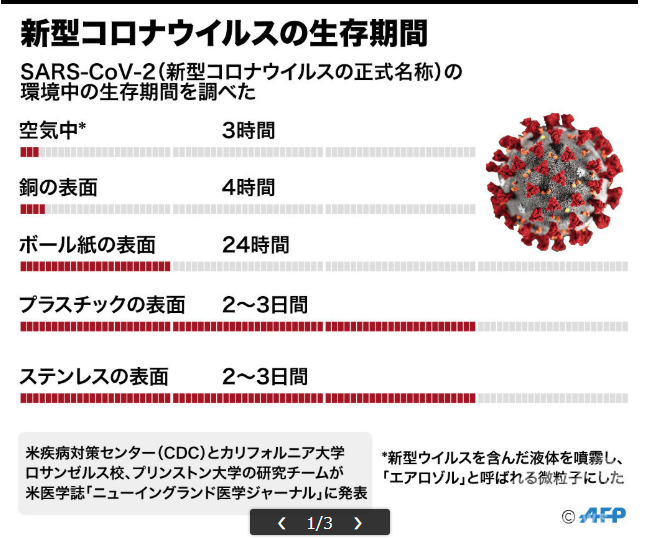こんにちは、今回は獣医師の阿部が担当いたします。
突然ですがクッシング症候群という病気をご存じでしょうか。
基本的にはワンちゃんの病気で発生率も高い病気です。アイビーでも治療中の子がたくさんいます。
今回はこのクッシング症候群について紹介させていただきます。
クッシング症候群は副腎という臓器から出るホルモンが過剰となり、さまざまな症状を引き起こす病気です。
よく見られる症状に、多飲多尿、多食、腹部の膨満、脱毛といったものがあります。

原因は、以下の2つの場合があります。
①脳の異常が原因の場合(クッシング症候群の85%)
下垂体(脳の一部)が異常に活性化し、「副腎ホルモンを分泌するように」という命令が過剰に出されているため、副腎ホルモンが過剰となっている状態です。
②副腎の異常が原因の場合(クッシング症候群の15%)
副腎が腫瘍となって、副腎ホルモンを過剰に分泌しています。
エコーやホルモン測定をしたりすることで、
「①脳の異常」「②副腎の異常」のどちらかをおおまかに推測することができます。
基本的な治療は多くの場合、内服による内科治療になります。
クッシング症候群の治療は、治すことではなく、生活の質の改善が目的となります。
しかし、治療によって、普通のワンちゃんと同じような生活をおくることができます。
クッシング症候群は『多飲多尿、多食』といった、病気と気づきにくい症状しかない場合もあります。
健康面で気になるところがあるときはぜひご相談ください。